![]() 大菊栽培(その1) もどる トップページにもどる
大菊栽培(その1) もどる トップページにもどる
| 1月10日 あけましておめでとうございます。 今年も仕事が忙しいので、どこまで菊に力を入れることができるかわかりませんが、頑張って育てようと思います。 現在の手持ち苗は 一文字(玉光院、新玉光院、岸の北極光) 厚物系(金越山、国華越山、富士の輝き、富士の新雪、国華80年、国華吉兆、国華八十天、太平の銀月、精興源流) 管物系(泉郷五色、泉郷情熱、泉郷白情熱、聖光の朝、聖光華宝) その他(北斎巴錦、元禄丸) ちょっと多すぎ。いつのまにこんなに品種が増えてしまったのでしょう。 |
 |
|||
| さて、冬至芽に硫黄石灰液の80倍を散布しました。 ところでウチダケミカルからの情報によると、中国産腐葉土が環境保護のため輸入禁止になり、今年は購入する腐葉土が全体的に不足し、高価になっててしまうとのこと。 あまり本気にはしていないが、とりあえず今度送られてくる国華園のカタログに同じ記載があったら本当だろう。 今年は腐葉土も作ってみようかな。 |
 |
|||
|
|
||||
| 1月10日 子供たちと歩いて15分ほどの近所の大規模公園に散歩に行きました。 子供と遊ぶというのは口実で、腐葉土のことがが気になっていましたので、本当の目的は公園にどんな落ち葉がどのくらいあるのかを調査しに行きました。 マテバシイ、スダジイ、クスの常緑広葉樹の林に入ってみると落ち葉がたくさん落ちていました。 常緑広葉樹の落葉時期は5月なのですが、半年間も清掃されていないで残っていました。 |
 |
|||
| 都市公園なので同じ樹木が計画的に植えられているため、落ち葉も他の樹木が混じっていない。落ち葉としては良質だと思う。 目の前に宝の山があるのだけれど、さてどうしようか。 腐葉土作りに挑戦したいのだが、都内の密集住宅街の中で発酵させることができるだろうか。 本日は、落ち葉の位置を確認するだけで帰ります。 さて今後は、家のどこで発酵作業をするかを考えることにします。そして発酵菌をバイムフードにするかウチダケミカル製にするかも考えよう。 なんだか楽しくなってきた。 |
 |
|||
|
|
||||
| 1月15日 国華園から会報が届いた。当然のことながら新花には興味はないのだが、古花のカタログを見ると国華横綱と泉郷富水からP登録が消えている。15年経つと権利がなくなるのですね。でも値下がりはしないのか。 新菊花会の競技花が『国華八十吉』で、これは自分で用意しなければならない。これのみを注文することにします。 気になる腐葉土ですが、ウチダケミカルが心配していたような影響はあんまりないみたいです。去年は国華園から大菊腐葉土(達人腐葉土の逆で荒い腐葉土)を注文していたのだが今回それは無くなった。とりあえず『落ち葉100%腐葉土』を注文することにした。 |
||||
|
|
||||
| 1月16日 ウチダケミカルに腐葉土の発酵菌を注文した。 バイムフードを使おうか迷ったが、ウチダケミカルならFAXすれば明日すぐ送ってくるので決めました。 |
||||
|
|
||||
| 1月17日 子供たちを連れてこの前調査した公園に落ち葉拾いに行きました。 土のう袋を3袋用意して、地表面の形の崩れていない落ち葉部分を集めました。 |
 |
|||
| 1袋目は子供たちも手伝ってくれたのですが、2袋目からは遊びに夢中になって、結局一人で集めることになりました。 歩いてきたので、なるべく荷物はコンパクトにしようと落ち葉を圧縮してみると2袋におさまってしまいました。 結構大量に集めたと思っていたのだが、腐葉土にしてみると最終的に土のう1袋もできないのではないのか。落ち葉集めも大変だ。 |
 |
|||
| 2袋では少ないと思うのだが、まずは試験的な腐葉土つくりなのでちょうど良い量なのかもしれない。 悪臭が出たとき近所迷惑にならないよう、積み込みは3階ベランダで行います。 葉っぱがカラカラに乾いていたので、袋ごと水槽に漬けて水分を吸収させまいた。 さて積み込みは次の日に行います。 |
 |
|||
|
|
||||
| 1月18日 腐葉土の積み込みをしました。 一晩水に浸かっていたいた落ち葉を取り出してみるとびっくり。 水が茶色に濁っている。タバコの吸い殻のニコチンやタールみたいです。 見る感じに有害のような気ががするのですが、本当にこの成分を抜いて良かったのでしようかね。 |
 |
|||
| 土のう袋の大きさから腐葉土の量を計算してみると約80リットルと試算された。 はじめての腐葉土作りなので、米ぬかや発酵菌の投入割合は、ウチダケミカルの資料を参考にすることにします。 米ぬかは4リットルと計算されましたので、正確に計りました。 ちなみに米ぬか1リットルは450gでした。 |
 |
|||
| 発酵菌も250gを正確に計りました。 とりあえず細かく計っておけば、今回の結果から2回目以降に調整するときに何かと便利なので。 |
 |
|||
| さらにバットグアノ800gを投入し、均等に攪拌しました。 ここで砂糖水を加えて予備発酵をさせれば初期発酵がスムースにいくところだが、ウチダケミカルの資料にはそんな手順は書いていないし落ち葉との混合時に米ぬかがダマになっていたら手間になりそうなのでやめておきました。 |
 |
|||
| さて、積み込む容器を以前から悩んでいたのですが、少量なので土のう袋に直接詰め込むことにしました。 落ち葉と米ぬかとクン炭4リットルを交互にまぶしながら詰め、大きな小枝やゴミを抜き取りながら手でギュっと体重をかけながら積み込んでいきました。 |
 |
|||
| 結局、土のう1袋になってしまいました。 あれだけたくさん集めたのにねえ。この1袋も発酵が進めば半分くらいになってしまうのだろうか。 |
 |
|||
| さて、保管場所は水を溜めていたボックスを利用することにしました。 通気性を良くするため底に網を敷いてから土のう袋を寝かせました。ちょうど良い大きさです。 |
 |
|||
| 土のうの周りをシルバーシートで囲んでから、初期温度を上げるための秘密兵器として、電気毛布を巻きつけてスイッチを入れておきました。 電気毛布は2年前にも赤玉土で試しているが、あの時は効果なかった。 |
 |
|||
| さらに全体をベタ掛けシートで囲って保温完了。 発酵もすぐにはしないし、すぐに酸欠になることはないと思いますので、しばらく様子を見ることにします。 大都心の住宅街で一番気になるのが悪臭ですが、はたしてどうでしょうか。 観察用の温度計を買ってこなければ。 |
 |
|||
|
|
||||
| 1月19日 前から気になっていた『育王』ですが、精光大臣さんの日記のレビューを見て思わず販売会社に注文した。 フリーダイアルに連絡してみると、育王は地方の農家をターゲットに販売しているので、東京都内に卸している園芸店はないとのことのこと。100cc、300cc、1000ccがあるが卸業者や農家が取引先なのでダース箱販売で、小売価格となることが原則とのことでした。趣味の園芸で個人的にほしいのだがと交渉すると、100cc、300ccのバラ在庫はないが、1000ccならバラ在庫があるので小売価格で販売しますとのこと。 値段を聞くと1000ccで小売価格6000円(ちなみに100ccは1000円、300ccは3000円)なので、予想外に安かったので思わず注文してしまいました。送料は確認していないけどおそらく別途だと思います。 住所を伝えてから郵送で振込書が送られてくるので、振込金額を確認後に発送するそうです。 個人で趣味のレベルで注文してきたことに相手もちょっとびっくりしていたみたいだけれど、電話対応もとても親切でしたので、全く気兼ねなく注文することができました。 実験の水栽培の準備をしなければ。 育王のHP http://www.ikuou.com/ |
||||
|
|
||||
| 1月20日 育王を注文した会社から請求書が届いた。 価格は1kgボトル7100円(本体6600円、運賃500円)に消費税で7455円でした。 小口販売でしたので送料はかかることはしょうがないです。地方のホームセンターでは店頭割引き価格となるのでしょうが、都内に売っているところがないのでいた仕方ありません。早速入金しておきました。 さて、2日間電気毛布で保温していた腐葉土ですが、温度計を中心に挿してみると、60℃あった。そして土のう袋の表面からは湯気が立ち込めていた。なんとか初期発酵に成功したみたいです。匂いも全くありません。 土のう袋の上下をひっくり返して、前回電気毛布があったっていなかった場所を保温しておきました。 |
 |
|||
| 追記 育王をネットでよく調べてみたら、農業資材の通信販売サイトに載っていた。価格は1Kgボトル6300円に送料578円でした。100g、300gも売っていました。 私は送金してしまったのでしょうがないですが、買われる方はこちらのサイトでご注文を! 日本農業システムオンライン |
||||
|
|
||||
| 1月21日 腐葉土の内部温度は55℃。高温発酵とは言えないようだ。温度によっては電気毛布を外そうと思っていたのだが、温度を少し下げ外周を保温しながら継続することにした。 |
||||
|
|
||||
| 1月22日 注文していた育王が届いた。有効期限が製造日から2年であるが、すでに1年経過している。 早く使わなくてはならないので、ケチケチしないで使えそうです。 |
 |
|||
|
|
||||
| 1月24日 腐葉土の状態を確認してみると、容器の下に水分が10リットルくらいたまっている。 おそらく発酵で蒸発して、ビニールシートに水滴として付着し、底にたまったのだと思う。 中心の温度をチェックしてみると30℃で、熱が落ちている。 |
 |
|||
| 中をあけてみると、白いカビが発生しているが、落ち葉はカラカラに乾いている。 積み込み前に1日ドブづけしたのに、水分が全くなくなっている。 水分補給をさせなくてはならない。 米ぬかが混じったところは、カサカサになって硬い塊になっている。これもほぐさなくてはならない。 |
 |
|||
| 土のう袋での腐葉土つくりはあきらめ、容器に広げて管理することにしました。ここで油粕も投入し、再発酵を促すことにしました。 密閉容器だと、失敗する可能性が高いと参考書に書かれていますが、切り返し回数を週2回程度にし酸素の供給を行い、発酵熱の補助と保温として電気毛布でサポートし、また、この容器の隅に1cmの穴を開けて、底に溜まる余剰な水分を抜き、腐敗を防ぐことにします。 気になる匂いですが、臭いにおいは感じられませんでしたが、新築の家の匂いのようなミントのような、清々しい香りが漂っていました。 |
 |
|||
|
|
||||
| 1月25日 育王のテストをするため、ホームセンターにヒヤシンスの球根を買いに行ったのだけれどすでに売り切れ。別のホームセンター3軒はしごしたのだけれど、時期が終わっていたので結局手に入りませんでした。 それでは代替品として園芸コーナーで探していたら、カイワレ大根があったので、私はこれで比較検討してみることにしました。 育王、メデネール、水の3対象区で、カイワレ大根100粒づつ載せ、発芽、成長、発根を調べてみたいと思います。 育王1000倍、メデネール100倍、ただの水 |
 |
|||
|
|
||||
| 1月29日 カイワレ大根が発芽しました。 何とも言えないような状況ですが、メデネールの発芽率が高いように思います。 |
 |
|||
|
|
||||
| 2月1日 双葉が緑色になっていきました。 メデネールが優位です。 育王はまあまあ普通です。ちょっと不安。 長男がインフルエンザにかかってしまいました。家族への感染を防ぐため、長男を別屋に隔離し、妻は家の中を除菌スプレーで入念に掃除しています。 でも、私はベランダで一生懸命、腐葉土の細菌を増やそうと努力している。 なんか、可笑しく思えてしまう。 |
 |
|||
|
|
||||
| 2月3日 オークションで菊づくり名人奥儀第三巻をゲットした。 盆栽菊には今のところ興味がないが、新しい菊花会の先輩が盆栽菊専門で、後継する人がいないようなのでちょっと勉強して習ってみようかなと考えて購入しました。 内容を読んでもあまり面白くない。まだ私の年齢ではちょっと早いと思うが、基本だけは知っておこう。 これで名人奥儀は全3巻揃ってしまった。 |
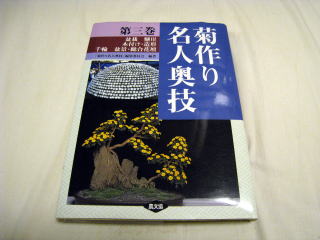 |
|||
|
|
||||
| 2月7日 育王の成長試験結果。 左から、メデネール、水、育王です。 発芽の良さは、メデネールがトップですが、スポンジを突き抜けている根は、育王がダントツでした。 でも、一番徒長しているのも育王ですので、なんとも言えません。 |
 |
|||
| 左から、メデネール、水、育王です。 なんとも言えませんが、メデネールが総合的には優秀な感じがします。 育王ですが、少なくともただの水よりは良い結果になっている。 もう一度実験をしてみる予定です。 さて、先日手に入れた菊作り奥儀第3巻を読んでいるのだが、いまいち興味が薄い。活字が頭に入らないのです。1巻2巻は、食い入るように読んでいたのに、やはり盆栽系は私にはまだ早いのでしょうか。 |
 |
|||
|
|
||||
| 2月11日 冬至芽の地際切りを行いました。 地際切りは、もう何年もやっているから、ためらいもなく大胆にカット。 傷の癒えた1週間後に硫黄石灰液で消毒します。 国華園から腐葉土が届いた。もちろん中国産です。 ウチダケミカルのかわらばんには中国産は今後入手できないと書いていたのに、あっさりと届いてしまった。 そして国華園のカタログには腐葉土の販売広告が通常通り載っている。 ウチダケミカルの中国産輸入禁止話はあまり信用できないが、自作腐葉土を作るきっかけとなったので、まあ良しとしよう。 ちなみに自作腐葉土は、週一回ペースで切り返して嫌気発酵を防止しています。やっと色が腐葉土っぽくなってきたが温度がいまいち上がらなかったので、米ぬかを1kg追加したところ熱くなってきた。 やっぱりちょっと米ぬかの酸っぱいにおいが気になるが、近所迷惑には全然ならないと思います。。 |
 |
|||
 |
||||
 |
||||